スマホ代、最近高くないですか? 子どもがいると通信量も増えるし、つい家計の固定費がかさんでしまう…。私も毎月の請求を見て「何とかしたい」と何度もつぶやいていました。格安SIMに乗り換えれば安くなるって聞くけど、手続きが面倒そうだし、電話番号や使い慣れたサービスが使えなくなるんじゃないかと不安で踏み切れないという声、よくわかります。
原因:なぜ乗り換えに踏み切れないのか
乗り換えに迷う理由はいくつかあります。まず「手続きが複雑そう」というイメージ。MNP(番号そのまま)の取り方やSIMロック解除、必要書類の準備など、用語だけで尻込みしてしまいますよね。次に「通信品質が落ちるのでは?」という不安。特に夕方や土日の混雑時間帯の速度低下を心配する声が多いです。また、長期契約の違約金や分割払い中の端末代金の問題もよく聞きます。
うちは最初、専門用語に圧倒されて保留にしてしまいました。
対策:具体的な準備と乗り換え手順
1) 事前チェック(準備)
- 端末のSIMロック解除が必要か確認:キャリアで購入したスマホはロックがかかっていることがあります。購入元のサイトや店舗で確認できます。
- 対応周波数の確認:使っている機種が乗り換え先の格安SIMで対応しているか、公式サイトでチェックしましょう。特に古い機種だと対応していないことがあります。
- 必要書類の用意:本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)、クレジットカードや銀行口座情報、MNP予約番号(電話番号をそのまま使う場合)を用意します。
2) どの格安SIMを選ぶか
- 利用データ量で選ぶ:家族で動画をよく見るなら大容量、通話メインなら音声プランを選択。
- 料金以外のサービスも確認:通話のオプション、キャリアメールが必要か、子ども向けフィルタやサポート窓口の有無。
- キャンペーンや無料お試し:お試し期間や初月割引を活用すると安心です。
3) 実際の乗り換え手順(一般的な流れ)
- キャリアでMNP予約番号を取得(※電話番号を引き継ぐ場合)
- 格安SIMの申し込み:公式サイトでプラン選択、必要情報を入力して申し込みます(eSIMならオンラインで完結する場合も)。
- SIM到着・SIM差し替え:物理SIMなら端末の電源を切って差し替え、eSIMならプロファイルをインストール。
- APN設定:格安SIMの案内に従ってAPN(ネット接続設定)を行います。近年は自動で設定される場合が多いです。
- 動作確認:電話発信、データ通信、SMS(必要な場合)の送受信を確認。問題なければ旧回線の解約手続きを進めます(自動で切り替わることも)。
私の場合、平日の午前中に手続きを始めて、翌日には新しいSIMで問題なく使えてほっとしました。
注意点:失敗しないために押さえておくこと
- 違約金・端末分割の残債:契約中の違約金や端末分割の残りがあるか確認。乗り換え前に思わぬ出費がないかチェックしましょう。
- 通話品質と速度:格安SIMは大手回線の一部帯域を借りているため、混雑時間帯は速度が落ちることがあります。動画視聴やテレワークが多い家庭は、速度の安定性を重視して選びましょう。
- キャリアメールや一部サービスの非対応:キャリアのメールアドレス(〜@docomo.ne.jp等)が使えなくなる、キャリア決済や一部の認証サービスが利用できなくなる場合があります。代替手段(Gmailやクレジット決済など)を準備しておくと安心です。
- 家族割や光回線セット割の喪失:今使っている割引がなくなる場合があるので、総合的に得するかを計算しましょう。
- サポート体制の違い:店舗サポートが少ないMVNOは自己解決が必要な場面も。初心者は店舗対応がある会社を選ぶと安心です。
うちは最初にキャリアメールをあてにしていて失敗したので、事前にLINEやGmailに移行してから切り替えました。
まとめ:スムーズに節約を始めるために
格安SIMへの乗り換えは、ちょっとした準備と手順を踏めば、大きな節約につながります。ポイントは「事前チェック」「自分の使い方に合ったプラン選び」「切り替え後の確認」。慌てずに手順を追えば、思ったより簡単に乗り換えられます。私も最初は不安でしたが、実際にやってみたら毎月の固定費が減って家計に余裕ができました。家族の通信環境を整えつつ、無理のない節約を目指しましょう。
うちは乗り換えで月々のスマホ代がぐっと下がって、子どもの習い事費に回せるようになりました。
読者が今日から試せる具体的な行動
- 今の請求書をチェックして「月の通信費」と「データ使用量」をメモする(まずは現状把握)
- 使っているスマホのSIMロック状態と機種名を確認し、対応周波数をメーカーサイトで調べる
- 気になる格安SIMの公式サイトで料金プランとお試し期間を比較し、申し込みに必要な書類リストを作る

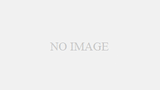
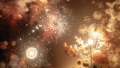
コメント